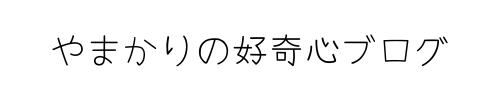”初心者向け”と紹介されることの多い丹沢大山。
ですが「初心者なら誰でも登れるの?」と聞かれれば、答えはNOです。
一言でまとめるなら【体力のある初心者向けの山】。
実際に筆者は40年間インドア派。登山歴もわずか2年目ですが、初めて挑戦したのが大山でした。
当然のように初挑戦は撃沈……。それでも1年後にリベンジして登頂を果たしています。
大山には複数のコースがあり、選ぶコースによって難易度は大きく変わります。
この記事では、初めて大山に登るなら知っておきたいポイントを紹介します。


見たい項目があったら目次で飛んでね!
大山の概要
神奈川県の大山(おおやま/標高1252m)は、丹沢山地の東南部にそびえる人気の山です。
山頂からは相模湾や富士山を望むことができ、晴れた日には雄大な眺望が広がります。
古くは「雨降山(あめふりやま)」と呼ばれ、信仰の対象としても知られてきました。
名物の大山豆腐や大山コマは、登山や観光の楽しみのひとつ。
日本三百名山や花の百名山にも選ばれており、四季折々の自然が魅力ですが、
特に秋は紅葉の名所として多くの人で賑わいます。

大山へのアクセス
大山は公共交通機関でもマイカーでもアクセスしやすく、
首都圏からの日帰り登山や観光に人気の山です。
登山口まで具体的なルートを事前に確認しておきましょう。
複数のコースがありますが、ここでは1番ポピュラーなケーブルカーを使うコースを紹介します。
電車・バス
最寄り駅の伊勢原駅までは新宿から小田急線で約1時間とアクセス抜群です。
伊勢原駅からは「大山ケーブルバス停」までバスで約30分です。
詳しくは公式サイトをご確認ください。
マイカー
伊勢原大山ICから約10分、秦野丹沢スマートICから約40分ほどです。
駐車場はありますが、土日や連休は朝早くから満車になることが多いです。
詳しくは公式サイトをご確認ください。
丹沢・大山エリアへお車でお越しの方|アクセス|丹沢・大山エリアナビ
大山はきついのになぜ初心者向けと言われるのか?
大山が“初心者向け”と紹介されるのは、ケーブルカーや整備された登山道など、
手軽に感じられる要素があるからです。
しかし実際は標高差が大きく、負荷が高いため、
運動習慣のない人にとってはかなりきつい山と言えます。
初心者向けは2種類ある
”初心者向け”は体力面と技術面で意味が異なります。
どちらに当てはまるかを知ることが、山選びの失敗を防ぐポイントです。
- 体力的に無理なく登れるコース
標高差が少なく、歩行距離も短めのコースが体力面での初心者向けコースと言えます。 - 整備されていて技術がいらないコース
登山道がしっかり整備されおり、迷いにくいので、技術がなくても登れるコースです。
大山が初心者向けに紹介される理由
- ケーブルカーがある
阿夫利神社下社まで標高差278mを一気に上がれるので、体力に自信がなくても安心して登れると紹介されます。 - 登山道が整備されている
石段や階段が整備されていて、道標も各所に設置されているため、迷いにくく、歩きやすいコースが多いです。 - アクセスが良く観光地化している
お土産屋やカフェ、茶屋が点在し、休憩ポイントも多いです。
実際に下社までならスニーカーでも観光に来れるので、敷居が低く感じます。
高尾山と比べるとここが違う
ここでは、同じく“初心者向け”と紹介される高尾山と大山を比較してみます。
| 山の名前 | 登り距離 | 登り標高差 |
| 高尾山(1号路) | 3.8km | 468m |
| 大山(下社~山頂) | 1.8km | 588m |
距離は大山の方が短いのに、標高差は高尾山よりも大きいんです。
つまり、短い距離で一気に標高を稼ぐ=傾斜がきついということ。
負荷だけで考えるなら、大山は初心者向けとは言えない山だと感じます。

初心者向けを鵜呑みして失敗した3つこと
初心者向けを盲信した結果、十分な下調べをせず、無謀な行動に繋がってしまいました。
ここからは、具体的な3つの失敗ポイントを見ていきましょう。
ケーブルカーの運行状況を確認していなかった
ケーブルカーに乗るつもりで登ったものの、運行開始前で利用できませんでした。
ケーブルカーなしで登ることに…
“初心者向け”とは、あくまでもケーブルカーを使った場合と知らなかったのです。
ケーブルカーの運行状況は、大山ケーブルカー公式サイトで確認できます。
ホーム | 大山観光電鉄 | 大山ケーブルカー公式ホームページ
コースごとの難易度を把握していなかった
コースよって距離や標高差が異なることを知らずに
「大山は初心者向けだから大丈夫」と思い込んでいました。
ケーブルカーを使えば、初心者向けの表参道コースですが、
ケーブルカーなしで登ると最も負荷の高いコースになってしまいました。
体力不足を考慮していなかった
普段運動していなかったため、体力は相当不足していました。
大山はかなり傾斜が急なので、階段を少し上がっただけでも息切れ。
登山経験も0だったのにも関わらず、“初心者向け”だから大丈夫と思い込んでいました。
筆者は無謀にもケーブルカーなしで登り始めましたが、阿夫利神社下社で断念し、ケーブルカーで下山しました。
無理せず引き返した判断は、登山を安全に楽しむ上で重要なポイントでした。

大山登山でのコース選び
大山には複数のコースがありますが、どのコースもそれなりの体力が必要です。
初心者向けと紹介されることが多いものの、体力や経験によって負荷は大きく変わります。
ここでは、初めて大山に挑戦する人が、自分の体力や経験に合わせて選びやすいコースと、
登山中に注意すべきポイントを紹介します。
登山初心者でも挑戦しやすいコースは2種類
大山で初心者でも挑戦しやすいコースは、
ケーブルカーを使った表参道コースと、
ヤビツ峠から登るイタツミ尾根コースです。
どちらも体力は必要ですが、
距離や標高差を知ることで、自分に合ったコースを選びやすくなります。
| コース | 距離 | 標高差 | コメント |
| 表参道コース (ケーブルカー利用) | 1.8km | 588m | ケーブルカー利用で短時間で登頂可能だが、傾斜が最もきついコース |
| イタツミ尾根コース (ヤビツ峠) | 2.1km | 507m | 大山の中では最も傾斜が緩やかだが、アクセスしづらい |
事前に確認したい情報
コースを選ぶ際には、次の情報を事前にチェックしておくと安心です。
- ケーブルカーの運行状況
運行時間や、点検などで終日運転しない日もあります。
大山ケーブルカー公式サイトで確認しておきましょう。
ホーム | 大山観光電鉄 | 大山ケーブルカー公式ホームページ - バスの時間
特にヤビツ峠へ下山する場合は、本数が少ないので事前に確認しておきましょう。
時刻表・運賃案内 | 利用者の皆さまへ | 神奈川中央交通 - 天気予報
雨や強風の日は登山リスクが高まります。
服装や持ち物の参考にもなるので事前に確認しておきましょう。
Windy: ウィンドマップ&天気予報 - 混雑状況
土日や連休中は、バス停に長蛇の列ができることもあります。
マイカーの場合は朝早くに駐車場が埋まってしまうこともありますので、
早めの行動を心掛けましょう。

持ち物・服装
大山は標高が1,200mを超えるため、天候や気温の変化が予想以上に激しいです。
安心して登るために、持ち物や服装を事前にしっかり準備しましょう。
基本の持ち物
最初のうちは必要なものを全て持っていないかもれませんが、少しづつ揃えていきましょう。実際に筆者も徐々に揃えていきました。
- リュック:軽量で背負いやすいもの
- 飲み物:体重50kgの人が6時間行動すると1.5L必要と言われています。
登山に必要な水の量と汗のはなし | 国産アウトドアブランドのファイントラック - 軽食:見かけよりエネルギーを消費するので行動食を持参しましょう。
- スマホ:YAMAPやヤマレコのGPSアプリを用意しましょう。
- 予備バッテリー:山ではスマホが命綱です。予備も必ず持参しましょう。
- 防寒着:季節にもよりますが、真夏でもウィンドシェルは持参しましょう。
- 雨具:できれば上下セパレートタイプのものが◎
- ファーストエイド:絆創膏やテープなど必要なものを準備しましょう。
- ヘッドライト:いざという時の備えです。出来れば準備しましょう。
服装のポイント
最初は登山用でなくても、速乾性のTシャツなどで充分です。
登山靴は欲しいところですが、実際スニーカーの方も多くいらっしゃいます。
しかし、おすすめはしません。
- 重ね着(レイヤリング):体温調節しやすく、速乾性のあるもの
- 動きやすいパンツ:伸縮性があり、動きの邪魔にならないもの
- 登山靴:トレッキングシューズや登山靴推奨
- 靴下:クッション性のあるものが望ましいです。
- 手袋:コースによっては手を使う箇所もありますし、防寒対策にもなります。
- 帽子・サングラス:山の日差しは強いです。紫外線対策にもなります。

大山登山の絶景カフェ「茶寮 石尊」
ケーブルカー阿夫利神社駅から行けるオススメのカフェ「茶寮 石尊」をご紹介します。
登山しなくても行けるので観光ついでに寄ってみてください。
筆者のお気に入りは「升ティラミス」升の中に抹茶のティラミスが敷き詰められています。
写真は升ティラミスと抹茶です。(抹茶好き)

さらにテラス席が絶景でオススメなのです。

お店は不定休なので、Xでフォローしておくといいかもしれません。
休業情報などを投稿してくれています。
公式X:@saryo_sekison
公式サイト:茶寮 石尊 – 大山阿夫利神社
まとめ
登山を楽しむには、コースや体力に合わせた計画、持ち物・服装の準備、休憩ポイントの把握が大切です。事前に情報を確認し、自分に合った無理のない登山を心がけましょう。